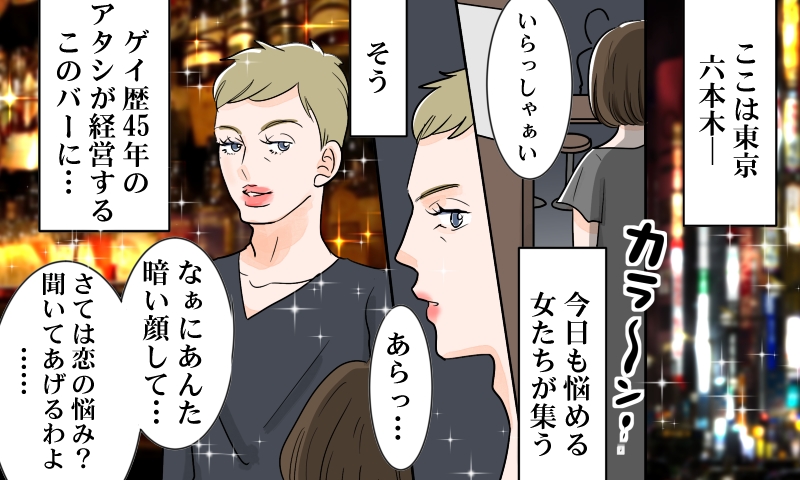【涙活】3分で泣ける実話ショートストーリー「アイスキャンディ」

ーー思い出の味、誰を思い浮かべますか?(DOKUJO文庫編集部)
3分で泣ける実話ショートストーリー「アイスキャンディ」
「お兄ちゃん。僕も付いていく。」
「パキッ。」
「待ってよ、お兄ちゃん。」
「パキッ。」
閉まりかけた店の前を通るたび、懐かしくて少し切ない思い出が浮かぶ。
私の実家は高台のてっぺんに建っていて、おつかいに行くときは長い坂道を下っていく。
幼少期には、よく父親のおつかいで、おばあさん一人で営んでいるすごく小さな駄菓子屋までタバコを買いに行った。
父親からはいつも少し多めのお金をもらい、タバコを買った後のおつりでお菓子を買うのが何より楽しみだった。

夏。アブラゼミの鳴き声よりも、クマゼミの鳴き声がうるさいとても暑い日だった。
四歳上の兄とおつかいを済ませた後、今日は何を買おうかなと思っていると、アイスケースが目に止まった。
その日はとても暑くて、私はこれから長い坂道を上って帰るのかと思うと、無性に冷たいものが食べたくなった。
「お兄ちゃん。アイスが食べたいよ。」
アイスを二本買えるだけのおつりは無かったので、兄がアイスを一つ選んで買ってくれた。
そのアイスは棒が二本通っていて、真ん中で割れば二本になるものだった。
早速袋から取り出して、二人で仲良く半分こ。
「パキッ。」
二本になった片方をもらい、夢中で食べた。
月日は流れ、私は結婚し父となった。
四歳の娘と、一歳の息子がいる。

実家は車で一時間少しのところで、割と頻繁に帰っている。先日、兄とよくおつかいに行った駄菓子屋の前を家族で通った。
あの頃の駄菓子屋は、今ではタバコだけを細々と売っており、店内はほとんど何もなく、時の流れと寂しさを感じさせた。
小さな駄菓子屋の周辺には、コンビニやドラッグストアが出来て、とても便利になった。
便利にはなったが、たまに何となく大事な何かを忘れてしまったような気持ちになる。
三月も終わりに差し掛かり、桜が満開で季節外れの初夏の陽気だった。
「今日は暑いから、アイスでも買って食べながら帰ろうか。」
大人になった私は、あまり甘いものが得意ではなくなっていて、アイスもほとんど食べなくなっていた。
子供たちがアイスを選ぶのを待つ。
「パパ。これがいい。」
渡された二本のアイスは、ソーダ味だった。
昔から変わらない、長い坂道をゆっくりゆっくり上りながら、まだ小さい息子のアイスを久しぶりに少し食べた。美味しかった。
兄は、娘が生まれる前に事故で他界した。
私は、昨年で兄の年齢を超えた。
兄ちゃん。こちらは元気でやっているよ。
今日、久しぶりにアイスを食べたよ。
よく二人で食べたアイスは販売終了になっていて、もう食べることは出来ないみたい。
僕はというと相変わらずで、今でもたまにあなたの姿をどこかに探してしまうんだ。
作:下倉健人(協力:あのころの味エッセイ大賞)
DOKUJO文庫編集部では、あなたの作品を募集しております。
info@sucmidia.co.jp宛にご応募ください。
採用された作品はDOKUJO文庫にて発表させていただきます。