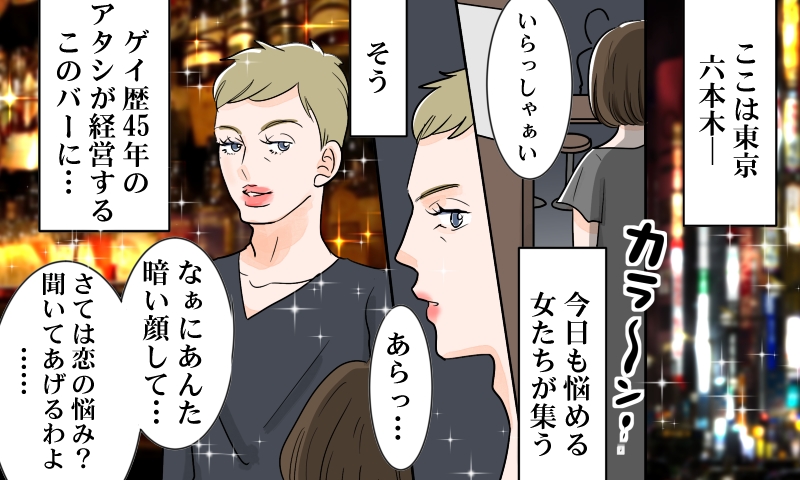アラサー女子のエッチなエピソード大賞!「一夜だけ結ばれた運命の人」前編

女子のみなさんから募集した「女子のエッチなエピソード」大賞。グランプリを受賞したエピソードが小説家・瀬音はやみさんにより小説になりました!
今回のテーマは「どうしても一緒になることができない2人~ 切ない最後のセックス」。是非ご堪能あれ!>
女子のエッチなエピソード大賞!「一夜だけ結ばれた運命の人」前編
「――じゃあ、テーブルのレイアウトはこんな感じでいいね?」
「え……ああ、うん。そうだね」
生返事した私をプランナーの男性がヘンな顔をして見ている。
それに比べて、話しかけた当人は何も気づいていないみたいにニコニコしたまま。
ぼんやりしていた私はふとわれに返った。ここはホテルで、私は今、婚約者と1ヶ月後に控えた結婚式の打ち合わせをしているんだった。
人の好さそうな笑顔の彼――正道との出会いは大学生のころだった。同じサークルで知り合って、互いにいつしか惹かれ合っていた。
あれから10年。なんとなく付き合っているうちに、適齢期とか何とか……要するに惰性で結婚することになったのだ。
「お義母さんの腰の具合はどう?」
「うん。だいぶ良くなったみたい」
「やっぱりさ、アヤちゃん家に近いマンションのほうが良かったんじゃない?」
「ううん、いいの。お母さんのほうが嫌がるって。でも、ありがとう」
彼が誠実で、私を愛してくれていることはたしかだ。仕事もマジメだし、公務員だから将来も安泰。友人たちも“純愛”を実らせた私たちをうらやましがっている。
でも……。
(これがマリッジブルーってやつかな)
そう、私はなんとなく気分が浮かなかった。
「平凡が一番。あなたは幸せ者だよ」
母の言葉が頭に浮かぶ。そうだよね、いまさらときめきがないなんて、ただのワガママ――いくら自分に言い聞かせても、やっぱり胸のわだかまりみたいなものは消えなかった。
今になって思えば、このときからすでに私は運命の出会いを予感していたのかもしれない。
明くる日、私はあるキャリアアップセミナーに参加した。大手メーカーのマーケティング部でアシスタントマネージャーをしていた私は、ひそかにITベンチャーへの転職をも考えていたからだ。
(だけど、結婚したらそんなことばかりも言っていられないんだろうな……)
私が結婚とキャリア志向のはざまに揺れていると、一人の男性が登壇した。
「今日お集まりのみなさんは、将来互いを高めあっていける友人です」
そんな切り口で語り始めたのが、鴻池弦(ゆずる)だった。
彼は、コンサルティング企業在職中に、外資系生保にヘッドハントされ、現在35歳にして人事マネージャーを務めるエグゼクティブ。そのかたわらセミナー講師をしているというヤリ手だった。
「ねえ、ちょっとイケメンじゃない?」
となりの見知らぬ女の子が話しかけてくる。私は曖昧に返事したけど、目は彼に釘付けだった。
みなぎる自信と輝く瞳、明晰な頭脳をうかがわせる語り口に、すっかり心酔してしまっていた。
「鴻池先生、私たちもっと先生のお話が聞きたいんです!」
「おいおい、先生はやめてほしいな。じゃあ、近くにいい店があるから――」
「やったー! みんなー、先生が一緒に行ってくれるって」
セミナー修了後、会場で知り合った数人が彼を誘ったのだけど、その中には私も入っていたのだ。
それから7~8人で彼を囲み、居酒屋の個室で乾杯した。同席したうち半分は女性だったけど、みんなキャリア志向だけあって積極的。私も負けじと彼に話しかけた。
「転職するのにやっぱり資格は取ったほうが有利ですか?」
「君の職種が必要とするならね。といっても、資格はあくまで手段にすぎない」
改めて彼と交わす言葉、間近に見るこぼれるような笑顔が私の心をかき乱していた。こんなにときめいたのは何年ぶりだろう。
気づけば、私は指導にかこつけて、彼と再会する約束をとりつけていた。このときすでに私は婚約者に対して心に秘密を宿していたのだ。
「今日も残業で遅くなりそう。電話も出られないと思うから、先に寝てて。彩夢」
正道にメールでウソをついたのも、どこか後ろめたい気持ちがあったからだろう。
それから2度ばかり、私は弦と2人きりで会った。といっても、もちろん話す内容は仕事のことが中心。それでも過ごす時間が長くなれば、おのずとプライベートも語り合うことになる。
彼に対する想いは募る一方だった。
私が婚約していることを打ち明けたのは、3度目の夜だった。
「そういえば、鴻池さんって結婚されているんですか」
「いいや。なんで?」
それは彼が車で私を家まで送ってくれている車中でのことだった。
「じつは私、来月結婚するんです」
できるだけさりげなく言ったつもりが、のどがつかえて声がカサついてしまう。
どうして今になってこんなことを打ち明けたのか――改めて自分の胸に訊ねる必要はなかった。わかっている、これ以上彼に心惹かれてしまう自分を隠すためであることくらい。
ハンドルを握り、まっすぐ前を見た彼はほほ笑んで答えた。
「おめでとう。そうだったんだ。なら、もっと早く言ってくれれば、みんなでお祝い――」
彼が快く祝福してくれるのもわかっていた――でも、お願いやめて。それ以上聞きたくない! だって私……
「彩夢ちゃん……」
こらえようとしても、どうしようもなかった。私は手で口を覆い、声が漏れるのはなんとか押さえていたけれど、あとからあとからあふれてくる涙は止まらなかった。
「大丈夫?」
心配した彼は車を停めて、ふるえる私の肩に遠慮がちに手を置いて慰めてくれた。
「ごめんなさい。私――」
彼にやさしくされればされるほど、胸が張り裂けてしまいそう。あなたが好き。
勝手に恋して、勝手に傷ついて。申し訳なさと恥ずかしさで身につまされていた。だって彼には全然関係ないのだから。
やっと少し落ち着きを取り戻した私は、ティッシュで涙を拭って顔を上げた。すると、そこに見つけたのは、複雑な表情を浮かべた彼の顔だった。
「じつは、俺も話しておきたいことがあるんだ」
いつになく沈んだ口調で彼が語り始めたのは、意外な事実だった。―(後編に続く)